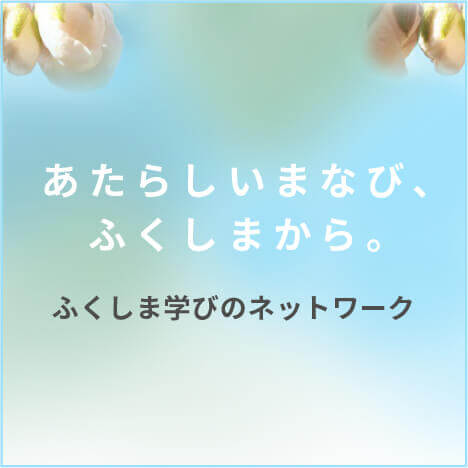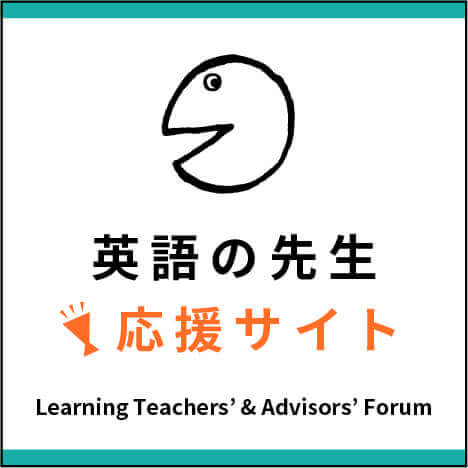3月25日。執筆中の『まるまる反復英文法総復習BOOK(標準)』があと2日か3日で脱稿となる(はずだ)。『ユメタン』にしても『東大英語リスニング』にしても、こんな本を生徒たちに採用したいなと自分で思える本を常に書いてきたが、この本もいい具合いである。
最近の英文法の本は、確かにルールを取り上げて問題にしてくれているのだけれど、原仙シリーズで育った我々にはどうにも薄口である。学校の施設と言えば「図書室(library)」や「職員室(teachers’ room」、出てくるのは「先生」や「生徒」が定番で、たまに誰だかわからない「彼」や「彼ら」も登場する。
stationの前には常にtheが付いていて、あたかもthe stationが決まった表現のようである。実際には「ある駅」について言及する場合、当然ながら a stationと英語では表現する。なのに文法の本では無条件にthe station。これでは生徒が英語で話したり書いたりする際に、どんな状況でもthe stationと言うのは避けられない。
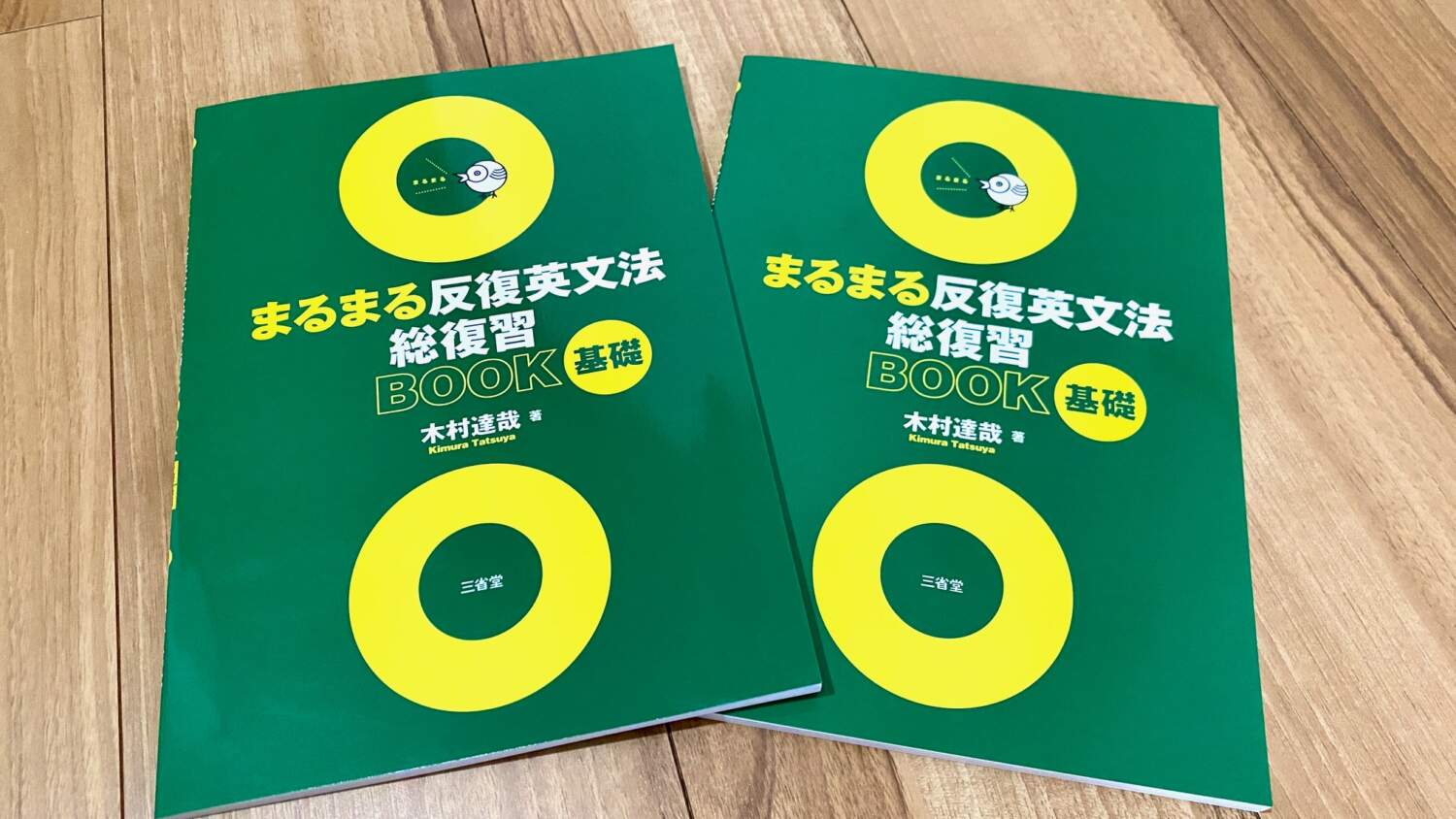
基礎編では冠詞の項目を作り、aとtheの違いについて何度も反復して学べるようにしたので、使っている生徒たちはおそらく「駅と言えばthe」なんてことにはならないと信じているが、このようなまったく文法の細部でもない当然の部分をしっかりと説明した本でありたいと思って書いている。
「分詞に修飾語句が付くと必ず後置」とか「仮定法でIf S were to Vは起こりえない未来を表す」などと私たちは昭和時代に教えられた。自分で英語の本や新聞を読んでいるうちに、そのルールは確定的ルールではなく、違うことなどいくらでもあることを自分で知ることになった。
であれば、自分が解説を書く際には、これは確定的じゃないよと、If S were to Vは「やらないとえらいことになるよ」というニュアンスを含むこともあるよと、ちゃんと書いてあげたい。細かすぎることは書かない。でも、正しいことは書かないといけないのではないか。
今日もひねもすPCに向かっていて、もう目が限界である。が、待っていてくださる方々もいらっしゃるだろうから、あと2日か3日は頑張ろう。終わったら少しだけビールを飲もうかな。
木村達哉
追記
メールマガジン「KIMUTATSU JOURNAL」を火木土の週3通無料配信しています。読みたいという方はこちらからご登録ください。英語勉強法について、成績向上のメソッドについて、いろいろと書いています。家庭や学校、会社での会話や、学校や塾の先生方は授業での余談にお使いください。